『スパイダーマン(2002年)』を再見しました。高校生以来です。
マーベルのヒーロー映画としては、もはや〝古典〟の1つに数えてもいいでしょう。ネタバレ全開で感想を書いていきます。ビターエンドの映画(※重大なネタバレ)にもかかわらず、はちゃめちゃにヒットしたという事実は嬉しくなりますね。「大衆娯楽の消費者は安いハッピーエンドじゃないと満足しないバカである」みたいな偏見を、気持ちよく笑い飛ばすような作品でしょう。
これは〝人生の岐路〟についてのお話です。
正直、初見の高校生のときにも「ちょっと古いタイプの映画だな」と感じました。
『マトリックス(1999年)』以降のハリウッドでは〝脚本革命〟が起きたという説があります。より情報量が多く、よりテンポの速い脚本が好まれるようになったというのです。その代表例が『ボーン・アイデンティティー』シリーズでしょう。とくに2作目の『ボーン・スプレマシー(2004年)』はその傾向が強く、20世紀の映画なら140分くらいになりそうな膨大な情報を、わずか108分でまとめあげています。
比べると『スパイダーマン』は古風です。
展開はゆっくりで、1つひとつのシーンをじっくりと見せるよう作りになっています。ビルの谷間をびゅんびゅんと飛び回るCGは今見ても爽快ですが、反面、格闘シーンはそんなにカッコ良くはない(※好きな人ごめんなさい!笑)。「スーツアクターがスーツを着て戦っている」感が満載で、キアヌ・リーヴスのワイヤーアクションを見た後では、ちょっと色褪せて見えてしまいました。
『スパイダーマン』は、表面的には子供向けの「ヒーローもの」です。しかし、トビー・マグワイアの演じるピーター・パーカーのキャラクター像は、かなり大人向けだと感じます。少年マンガよりも青年マンガっぽい。
主人公らしい主人公というのは、強烈な〝欲求〟や〝願望〟を持ち、それに向かってなりふり構わず行動するものです。
ピーターは、そういう王道な主人公ではないのです。
日本のマンガから例を引きましょう。たとえば『僕のヒーローアカデミア』のデクくんは「オールマイトのようなヒーローになりたい」と願い、そのためになりふり構わず行動します。『鬼滅の刃』の竈門炭治郎は「妹を人間に戻したい」と願い、そのためになりふり構わず行動します。ちょっと変わった例では、『孤独のグルメ』の井之頭五郎も同じです。心穏やかに、静かに食事をしたいという欲求を持っており、それを邪魔する店員に対してアームロックまで決めてしまう――つまり、なりふり構わず行動するのです。
ところがピーターは、そんな人物ではありません。
表向きにはMJと恋仲になりたいと願っていますが、それを実現するためにどんな行動をするでしょうか? たとえば炭治郎は(勝てるはずのない)冨岡義勇に飛び掛かっていきました。そういう「なりふり構わない行動」を、ピーターはしているでしょうか?
MJの気を引くために自動車が欲しい。そのためにお金が欲しい。そのためにレスリングの大会に参加して賞金を得ようとする――。
要するに、めっちゃくちゃ遠回りしています。
ピーターは、願望の実現のためにアクションを起こすような主人公ではありません。どちらかといえば、周囲の状況に流されて、リアクションばかりしているタイプのキャラクターです。脚本の教科書的に言えば「こういう主人公を書いてはいけない」というダメな例になってしまうでしょう。けれど、私たち観客は、そんなピーターに感情移入せずにはいられないのです。
なぜでしょうか?
ピーターがアクションを起こせないのは、親に止められているとか、性別が同性であるとか、遠隔地に住んでいるとか、そういう物理的な障害があるからではありません。ピーターの願望実現の障害になっているのは、ピーター自身です。物語開始時点では、彼は自分に自信が持てません。というか、自分がどういう人間なのか、自分でも理解できていません。
つまり、ピーターの表向きの願望は「MJと恋仲になりたい」ですが、本当の願望は「自分が何者なのかを知りたい」なのだ……と私は解釈しました。『スパイダーマン』は、まだ半分子供だった主人公が、自分が何者であるか、自分が誰なのかを発見していく物語です。時代や地域を超えて普遍的なテーマを扱った映画だと見做せるはずです。
人間の人生には流れがあり、段階があります。それら各段階――つまり〝人生の岐路〟を扱った映画は1つのジャンルになっています。たとえば結婚前夜の『ハングオーバー』、離婚前夜の『クレイマー、クレイマー』、中年の危機を描いた『アメリカン・ビューティー』や『LIFE!』。
私見では、こういう〝人生の岐路〟タイプの作品では、主人公の願望はさほど強くありません。というか、「自分は誰なのか知りたい」「人生の目標が欲しい」「意味ある何かを残したい」のような、抽象的でなかなかアクションに繋がりにくい願望を、このタイプの作品の主人公は抱きます。『スパイダーマン』もこのジャンルに(私は)分類したくなります。
『スパイダーマン』が描く〝人生の岐路〟は「思春期の終わり」です。
子供の時間はここでおしまい、ここからは大人にならなければダメ、という瞬間。「自分が何者であるか」に気付く瞬間。それが思春期の終わりです。
自分が何者なのか分からない子供だったピーターは、最後にはあれほど好きだったMJをフります。自分と一緒にいると、彼女が危険にさらされると思い知ったからです。「大いなる力には大いなる責任が伴う」「僕はスパイダーマンだ(I'm Spider-Man)」というセリフでこの映画は終わります。
男の子なら誰しも、思春期のある時点で気づきます。母親や姉妹や恋人を殴れば、自分のわがままを押し通せるのだと。自分にはそれだけの筋力があるのだと。
では、なぜそうしないの?
「大いなる力には大いなる責任が伴う」からです。
ピーター・パーカーは、もう1人の俺たちです。
女の子だって同じでしょう。嫌いな教師がいたとして、彼にセクハラされたと訴えれば彼の人生を破滅に追い込めると気づく瞬間があります。自分の下着の写真をちらつかせれば、いい歳の男たちを意のままに操れると気づく瞬間があります。自分の〝力〟を自覚する瞬間があるはずです。
では、なぜそうしないの?
「大いなる力には大いなる責任が伴う」からです。
ピーター・パーカーは、もう1人の私たちです。
ヒトは人生のある段階で、自分の持っている力に気付きます。その力の使い方に注意しなければならないと自覚します。『スパイダーマン』の根底に流れている哲学/テーマは普遍的であり、なおかつ日常では忘れがちなものです。だからハッとさせられるし、感情移入させられるのでしょう。
『スパイダーマン』の脚本は本当によく出来ていて、すべてのエピソードが「大いなる力には大いなる責任が伴う」というテーマに繋がるようになっています。たとえば、レスリング大会に出るシーンに戻りましょう。ここでピーターは約束の賞金を受け取れません。可哀想です。脚本家のデヴィッド・コープは、意地悪く、主人公の欲しいものを目の前から取り上げます。
しかし、よく考えてみましょう。ピーターがレスリング大会に参加するのは、徹頭徹尾、自分のためです。好きな女の子の気を引くためにクルマが欲しくなり、その軍資金として賞金が欲しくなる。自分の得た〝力〟を、自分のために使ってしまう。
その結果、望みが叶えられないどころか、最悪の事態を招いてしまいます。
もしも「ピーターが賞金を受け取る」という展開だったら、観客の目にはどういうメッセージとして映るかを考えてみましょう。与えられた〝大いなる力〟を、自分のために使ってもいいんだ! というメッセージになってしまうかもしれません。「大いなる責任が伴う」という本作のテーマが弱められてしまうのです。
グリーン・ゴブリンの野望が〝ショボい〟のも、このテーマと関係しているでしょう。
ゴブリンは世界征服とか人類絶滅とか、そういう本当にヤバい目的は抱いていません。何をするかは具体的には決めていないけれど、まずはピーターを仲間に引き入れたいと考えます。そして、それが叶わないと知って、暴虐の限りを尽くします。
ヒーローものの悪役は、しばしば「鏡に映ったもう一人の主人公」として描かれます。グリーン・ゴブリンは「暴力でわがままを通す」ことを選んだもう一人のピーターなのです。
作劇上、ゴブリンは「暴力でわがままを通す」という行動を徹底することで、スパイダーマンの好対照をなすように設定されています。世界征服とか人類絶滅みたいなデカい野望を持たせてしまうと、スパイダーマンとの対照性がボヤけてしまう……と脚本家は判断したのでしょう。
細かいところに目を向けると、まずセリフの1つひとつが端的で力強く、カッコいいですね。「大いなる力には大いなる責任が伴う」が一番有名ですが、121分間ずーっと名台詞が続くみたいな感じの映画だと感じます。要求される英語力はそんなに高くありません。吹き替えを作るほどの需要が見込めない言語圏の人でも理解できるはず。
また、細かい脚本のテクニックでは「無理やり葛藤」と呼ばれるテクニックの好例を確認できます。
長い説明シーンは退屈になりがちです。〝ドラマとは葛藤である〟という原則に従えば、解説シーンに何かしらの葛藤を(無理やりにでも)重ねることで、退屈になるはずのシーンを面白くできる……というテクニック。それが「無理やり葛藤」です。
映画冒頭の、大学で蜘蛛の能力について解説を受けるシーン。蜘蛛の跳躍力や、糸の強靭性、第六感を持っているかもしれないという仮説……。そういう退屈な解説を背景に「MJに声をかけたいけどかけられない」「同級生にからかわれるけどやり返せない」というピーターの葛藤を重ねています。熟練の技。
じつのところ『スパイダーマン』で語るべきは続編の『2』のほうかもしれません。
脚本家ブレイク・スナイダーは、ハリウッドでは珍しい〝前作よりも面白い続編〟の1つだと評しています。『ゴッドファーザー』や『ターミネーター』『エイリアン』等と並ぶ「続編なのに傑作」が、2004年に公開された『スパイダーマン2』だというのです。
前作『スパイダーマン』では〝責任〟を果たす方法としてピーターは「MJから離れる」という選択をしました。
でも、それって本当に正しい責任の果たし方なの?
責任を果たすってどういうことなの?
これが『2』の中心的な問題提起です。
脚本家としては危険な賭けだったんじゃないかと思います。というのも、前作でピーターは「MJと付き合わない」という選択をしたわけです。「でもやっぱりMJと付き合いたい」という姿を見せてしまうと、前作での成長が無かったことになってしまう……ように見える危険があります。
でも、『2』のピーターはそう見えません。
結局、人間は思春期を終わらせても、すぐには大人になれないということなのでしょう。自分は何者なのか、どんな人物になりたいか。それを理解しても、実際に理想通りになれるとは限りません。理想と現実との乖離に『2』のピーターは苦しみ続けます。
『2』は、典型的な〝ヒーローの孤独〟を描いた作品でもあります。
「自分がスパイダーマンであること」を隠し続けることで、ピーター自身はもとより、MJやハリー、おばさん等の周囲の人々も不幸になっていくのです。絡み合った糸をほぐすには自分の正体を明かすしかない状況へと、ピーターは追い込まれていきます。
サム・ライミ版『スパイダーマン』の否定的な感想として「ヒロインMJが魅力的に見えない」というコメントをしばしば見かけます。なんというか、その気持ちはよく分かります(笑)。
ヒーローもののヒロインにしてはあまり貞淑ではないというか、次々に男をとっかえひっかえしているんですよね。「他の男と付き合いながらも心の奥底ではピーターを想い続けている」という設定自体はファンタジーなのですが、ファンタジーに徹することなく、変なところで現実的です。
これは世代の問題かもしれません。
じつは『スパイダーマン』が公開されたゼロ年代の前半は、若者が今よりもずっと性に奔放な時代でした。少なくとも日本では、デートの経験、キスの経験、そしてセックスの体験のどれをとっても、過去半世紀でもっとも若者が積極的だった時代なのです。
つまり当時高校生だった私たちにとって、ピーター・パーカーやMJの体験は決して他人事には思えなかったのです。すでに恋人がいる人を好きになってしまって、どうやって略奪愛しようかと考える。あるいは他に好きな人がいるけれど、告白されたからお試しで付き合ってみる――。そんな行動がごく普通に見られる時代でした。
冒頭で書いた通り、『スパイダーマン』はもはや現代の古典です。
こういう時代背景の違いも感じながら見ると、より楽しめると思います。
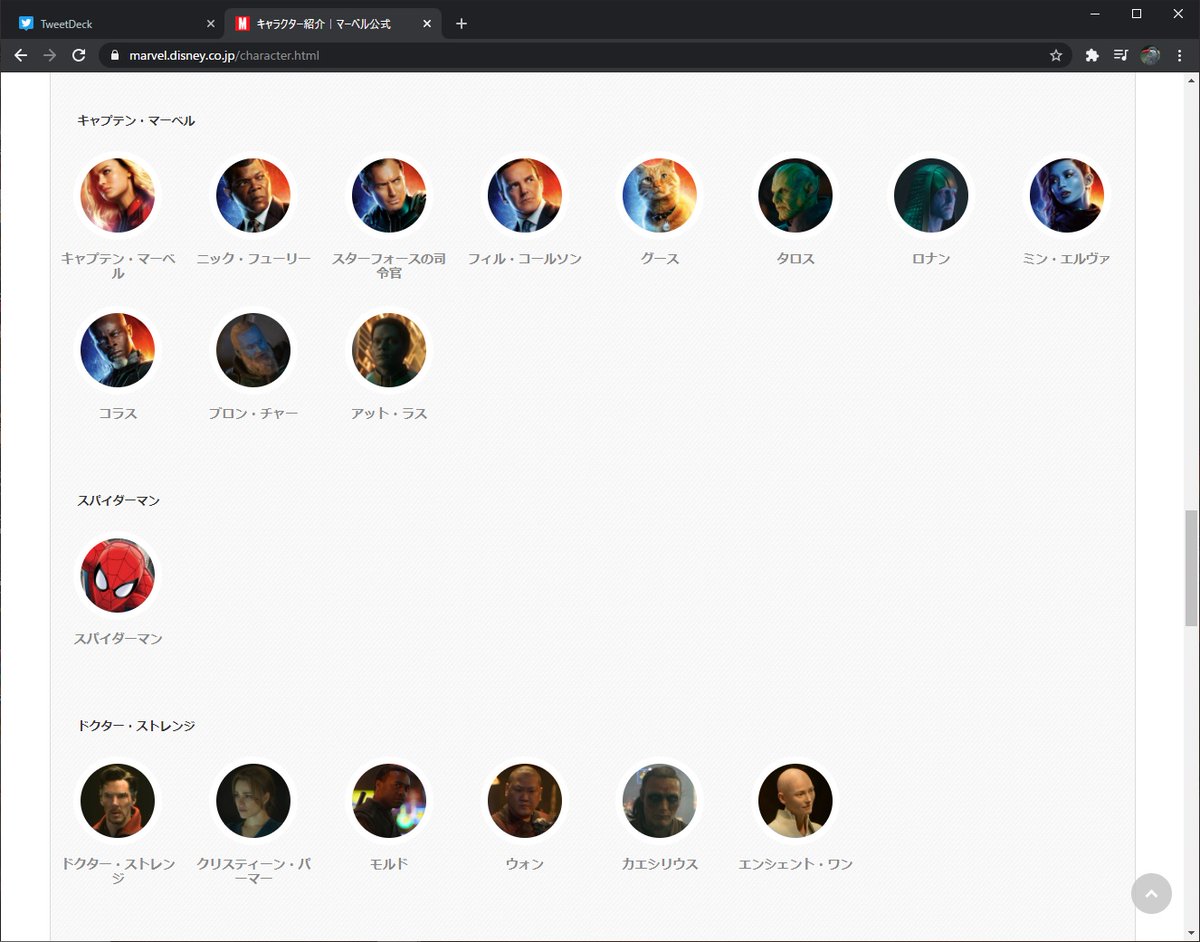
スパイダーマンはマーベルヒーローの中でも少し異色というか、「カッコ良い」よりは「気持ち悪い」寄りのヒーローです。公式サイトでも1人でハブられていて、ちょっと可哀想です。アベンジャーズの欄はあんなに賑やかなのに……。
億万長者のトニー・スターク。神の息子のソー。伝説的な第二次世界大戦の兵士スティーブン・スティーブ・ロジャース。
一方のピーター・パーカーは蜘蛛に噛まれたオタクです。設定だけ聞くと、カッコいいところが何一つありません。しかし素晴らしい映画化により、ピーターは誰からも愛されるヒーローになりました。
★お知らせ★

新連載『神と呼ばれたオタク』が、くらげバンチにて始まりました。
毎週火曜日更新の予定です。よろしくお願いします。


